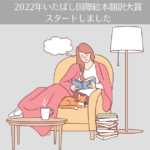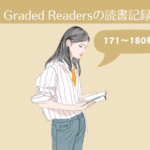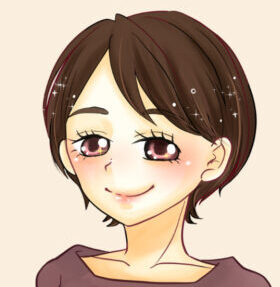英検1級に合格した主婦です。英語学習経験をブログにしています。
2020年12月から、日本和装の着付無料教室に通い始めました。
今回は2回目のレッスンです。
第2回目のレッスン

日本和装での第2回目のお稽古です。
持ち物は、着付け道具一式、着物、袋帯なので、着物に必要なものすべてです。
着物用バッグに全てをいれると本当に重い。
肩が凝りそうになりながら教室に到着しました。
前回の復習(着物の着付けまで)
今回も先生と、生徒2人の計3人でのレッスンです。
まずは前回の復習を兼ねて着物の着付けをしました。
家で1回練習してきたので、先生にアドバイスをいただきながらもなんとか着ることができました。
でもまだ練習が必要なレベルです。
袋帯のお稽古
着物の着付が終わると、今回のメイン「袋帯」のお稽古です。
袋帯は、子どもの小学校入学式で使いました。
だからその当時は袋帯が結べたのだと思いますが、もうほとんど覚えていなくて、先生から「タレ」や「手先」という言葉をきいても、どっちがどっちだっけ・・・
と思うくらい忘れていました。
袋帯、大変そうだな・・・
と思いつつ先生からの説明をお聞きしました。
先生が少しずつやり方を見せてくれて、それに合わせて自分でもやってみます。
見てわかったつもりでも、実際に自分でやってみると帯はとくに難しいです。
なんとか先生に助けられながら袋帯を結ぶことができました。
途中みんな必死で暑くなって、部屋の暖房を消してもらいました・・・
新鮮だったのは、日本和装の袋帯の結び方です。
折りたたむようにして帯をつけていきます。
物理的に帯を結ぶ(しばる・ねじる)ことをしません。
「帯をしばらなくて、きっちりと帯が留まるのかな?」
と思いましたが、つけてみると意外としっかり留まっています。
これならズレることもなさそうです。
以前ほかの教室で習ったときは、帯を物理的にむすぶ(しばる・ねじる)方法で、これがけっこう苦手でした。
しばった帯を両手で力一杯ひっぱるのがシンドくて疲れてしまうのです。
それにいい帯だと、しばって傷まないのか気になっていました。
もしかすると帯を物理的にしばったほうが帯がズレないのかもしれません。
でも、しばらなくても帯がつけれるのであれば、わたしはその方が楽でいいです。
袋帯をもう一度お稽古
袋帯が一応は結べましたが、時間があったのでもう一度やってみることになりました。
覚えの悪いわたしは2回目でも記憶があいまいで、先生に確認しながらやっと結べました。
それでも日本和装の袋帯の手順は、こころなしか今まで習った方法に比べると簡単に感じます。
あと2、3回お稽古すればなんとか着れると思います。
これなら年始に着物を着れそうなので楽しみになってきました。
お稽古が終わって
お稽古が終わって、しばらく先生から着物にまつわるお話を伺いました。
羽織や道行きのこと、着物と帯の組み合わせなど。
着物のこういったお話は本当に興味深く、お稽古の楽しみのひとつです。
先生はとても着物がお好きで、知識もある方のようです。
教室を出て
教室を出てから、もう一人の生徒の方とお話しする機会がありました。
お互い気になっていたのが、近々開催される「セミナー」です。
以前の記事でも触れましたが、「セミナー」とは、ふだんのお教室とは別の場所で、実際の着物や帯を見ながら生産者のお話をお聞きし、そのあと販売会に参加するというもの。
「丸一日の日程で時間的にきびしい」
「販売会がセットになっている」
「コロナの状況が心配」
など、お互い同じような心配を持っていました。
とくに販売会については、もう一人の生徒の方も私と同様に、着物や帯の購入予定がないそうです。
そのことが今後のお稽古に響かないのか気になっているということでした。
セミナーの心配はありますが、着物生産者の方からのお話や、実物を存分に見れる機会は楽しみでもあります。
コロナの状況がひどくならない限り日程を調整してセミナーも参加してみようと思います。
次回のお稽古も袋帯です。